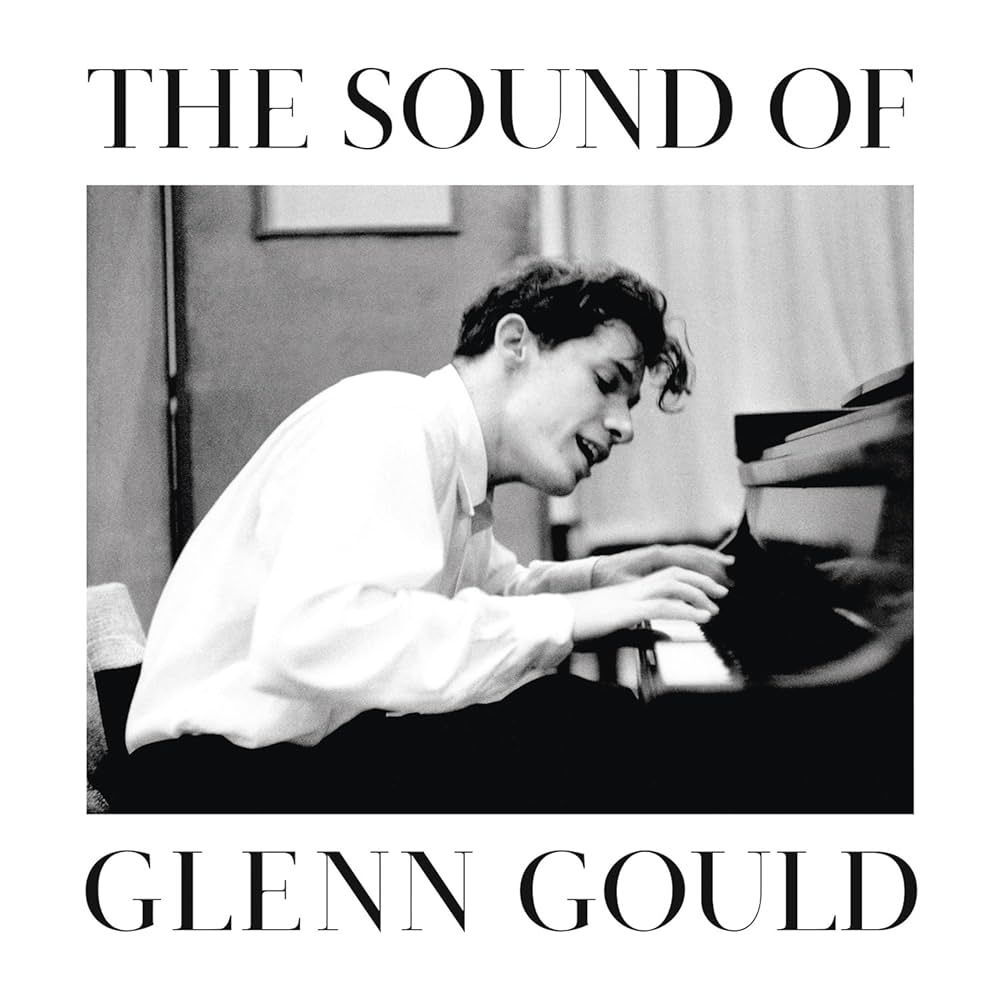9月25日は、カナダ出身の天才ピアニスト、グレン・グールドの誕生日(1932-1982)。
ロックばかり聴いてきた私(コヨーテ)にとって、クラシックは正直「退屈そう」というイメージだった。
しかし、グールドの演奏に出会ってから、バッハがまるでロックンロールのように生き生きと響きはじめたのだ。
バッハを「キラキラ」させた男
とにかく有名なのは《ゴルドベルク変奏曲》。
デビュー盤(1955年)では疾走感とスリル、再録音(1981年)では孤高の境地。
同じ曲とは思えないほど対照的で、どちらも傑作。
さらに《平均律クラヴィーア曲集》《シンフォニア》など、どんな教科書的な曲も、
彼の指にかかれば生き物のように動き出す。
それまで「退屈な教会音楽」と思っていたバッハが、
一気にキラキラ、ドキドキする音楽になった瞬間だった。
グールドの“異端児”エピソード
・ライブ嫌い:32歳でコンサート活動を完全にやめ、録音に専念。
・鼻歌:演奏中にハミングが止まらず、録音エンジニア泣かせ。
・独自スタイル:低すぎる椅子、奇妙な姿勢、徹底した完璧主義。
「自分の理想の音楽は録音でしか実現できない」と言い切った男。
この時代にもし生きていたら、きっとYouTube配信やAIミックスまで自分でやっていたに違いない。
バッハ&ロマン派おすすめ盤
• バッハ:パルティータ全集
ゴルドベルクや平均律よりも少し肩の力が抜けた、舞曲の楽しさ全開の演奏。
グールドらしいスキップするようなリズム感がクセになる。
• ブラームス:間奏曲集 Op.117, Op.118, Op.119
晩年の内省的な小品集を、これ以上ないほど冷たく、しかし透明に弾き切る。
秋の夜に聴くと、胸が締め付けられるほどの孤独感が漂う名演。
• ベートーヴェン:ピアノソナタ第30〜32番
晩年ソナタの精神性を、極端なテンポと異常な集中力でえぐり出す。
第32番の終楽章アリエッタは、まるで祈りのよう。
• シューマン:ピアノ四重奏曲 変ホ長調 Op.47
グールドがジュリアード弦楽四重奏団と共演した、まさに名演中の名演。
第1楽章の冒頭から引き締まったテンポ、精密機械のようなアンサンブル。
しかし緩徐楽章では、シューマンらしい甘美な旋律がまるで遠くの夢のように漂う。
ジュリアードのストイックな響きと、グールドの切り込むようなピアノがぶつかり合い、
結果としてこの曲が持つ「光と影」が鮮やかに浮かび上がる。
コヨーテ的まとめ
クラシックの「入り口」は退屈なものじゃなくていい。
むしろ、グールドのように「ちょっと変わった人」に導かれた方が面白い。
バッハを聴き始めるなら、まずはゴルドベルク変奏曲1955年版でしびれてほしい。
そこから平均律、パルティータ、ブラームスの間奏曲集…と広げていけば、
ピアノの世界が一気に開けるはず。