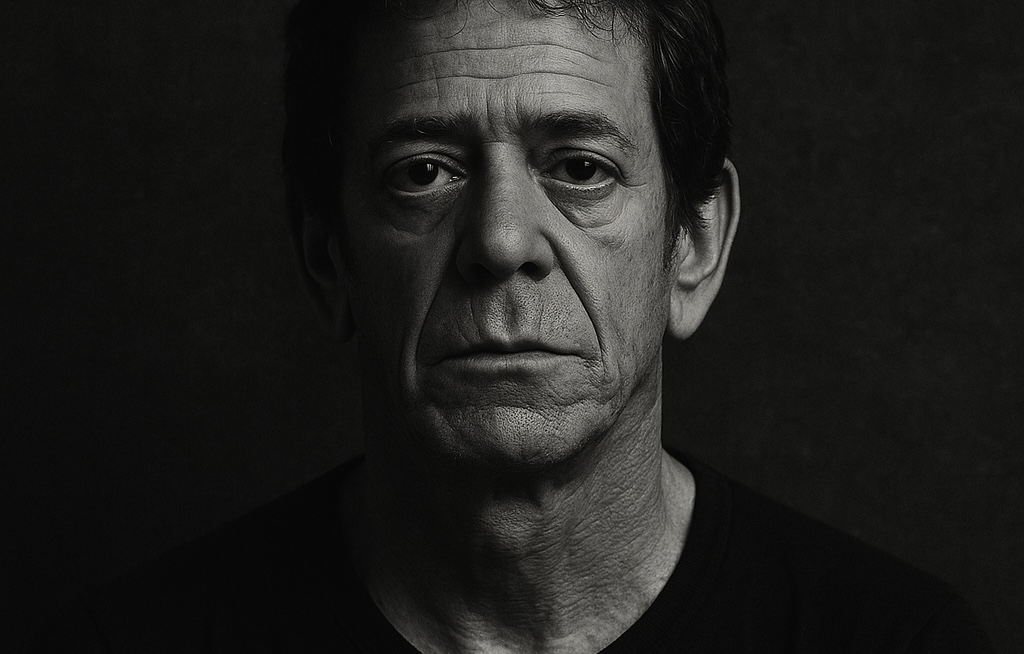見るからに不健康そうで、笑顔を見せることも少なかったルー・リード。
だが彼の音楽は、ロックの裏側、街の片隅に生きる者の痛みや矛盾を、見事なまでに芸術に昇華した。
ヴェルヴェット・アンダーグラウンドが与えた衝撃は、ビートルズやストーンズにも匹敵する。
そしてルーがソロになってからの道のりもまた、ロックの“影と光”を行き来する旅だった。
ソロ転向と「裏通りの詩人」誕生
ヴェルヴェッツ解散後、ルーは1972年にセルフタイトル作『Lou Reed』で再出発。
同年の**『Transformer』では、プロデューサーにデヴィッド・ボウイとミック・ロンソンを迎え、彼の代名詞ともなる「Walk on the Wild Side」**が生まれる。
性的マイノリティやストリートの人々を淡々と描くその語り口こそ、ルー・リードの真骨頂。
“普通じゃない人たち”を、憐れまず、誇張せず、ただ美しく描いた。
電子音とノイズへの接近 ─『Berlin』『Metal Machine Music』
1973年の『Berlin』では、愛と破滅の物語をシアトリカルに構築。
重苦しいテーマとストリングスを交えたサウンドは、当時酷評されたが、のちに再評価される傑作だ。
そして1975年、問題作**『Metal Machine Music』**。
ギターのノイズだけで構成されたこのアルバムは、もはや“ロック”ではなく“現代音楽”。
聴く者を突き放しつつも、「芸術とは何か?」を突きつけた。
“愛”を語るルー ─『Coney Island Baby』からの静かな祈り
ルーの中にある優しさが滲み出るのが、1976年の**『Coney Island Baby』**。
同名曲では、こう歌う。
“I’d give the whole thing up for you.”
(すべてを君のために捧げよう)
破滅と皮肉の裏に、ルーはいつも“純粋なロマンチスト”を隠していた。
終末感と再生 ─『New York』『Magic and Loss』
80年代後半、彼は再び街に戻る。
**『New York』(1989)は、政治と社会を鋭く切り取った都会のドキュメント。
ルーの語りはジャーナリズムの域に達し、まるで新聞のコラムのよう。
そして1992年の『Magic and Loss』**では、友人の死をテーマに、静かに人生を見つめ直す。
「What’s Good」や「Cremation」は、彼の晩年の哲学そのものだ。
ルー・リード名曲6選(ソロ期)
1. Walk on the Wild Side(Transformer/1972)
2. Perfect Day(Transformer/1972)
3. Sad Song(Berlin/1973)
4. Coney Island Baby(Coney Island Baby/1976)
5. Dirty Blvd(New York/1989)
6. What’s Good(Magic and Loss/1992)
どれも“ルー・リードにしか書けない詩”が宿る。
退廃的で、冷たく、でもどこか人間くさい。
それがルー・リードという男だった。
余韻──静かな別れと永遠の影
ルーは2013年10月27日、71歳でこの世を去った。
彼の死後、ローリー・アンダーソンが語った言葉がある。
“ルーはとても幸せそうだった。最後までアーティストとして生きた。”
音楽が“影”を描くことを恐れない限り、ルー・リードは永遠に生き続ける。
ウォーク・オン・ザ・ワイルド・サイド──彼の足跡は、いまも都会の路地裏に響いている。