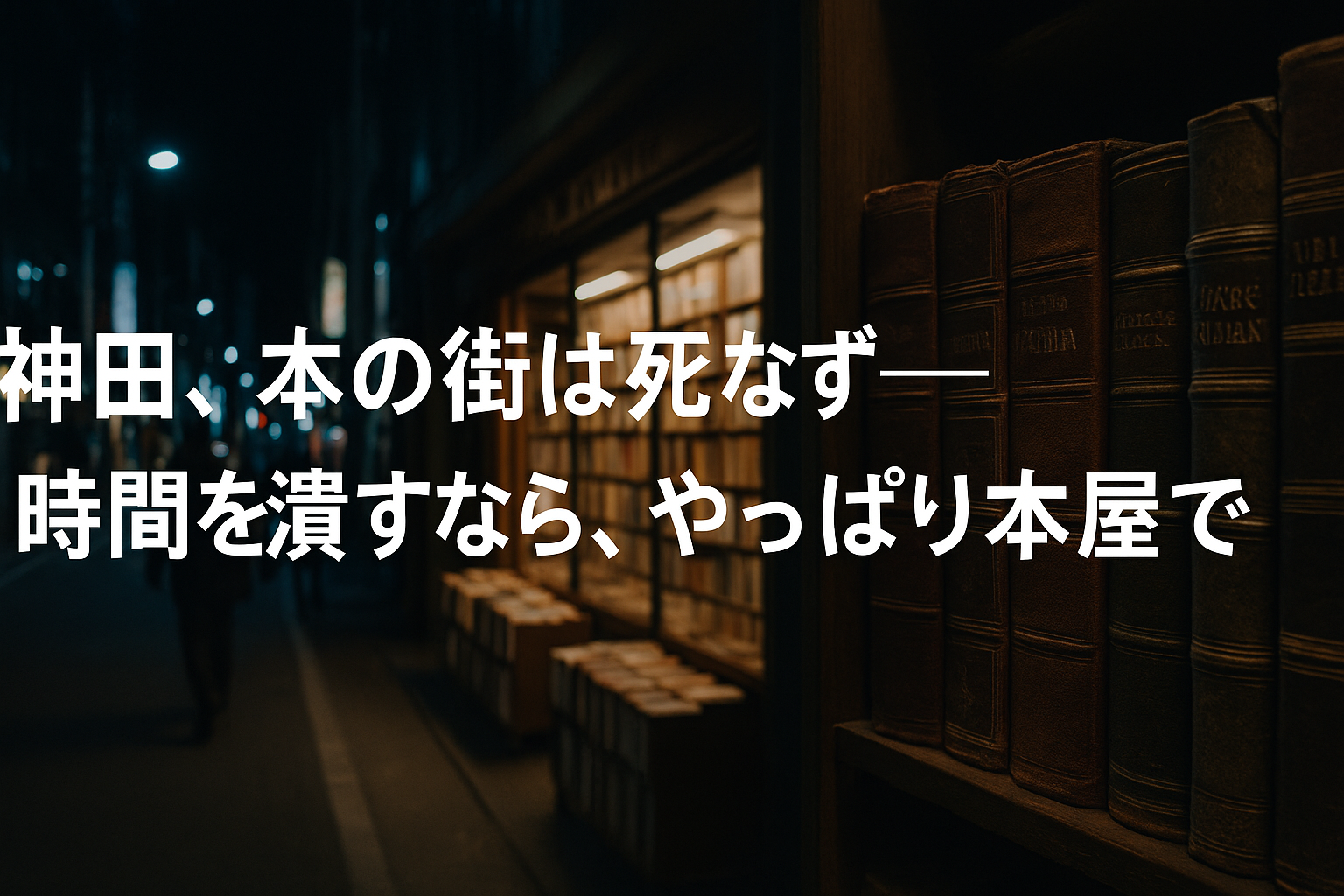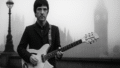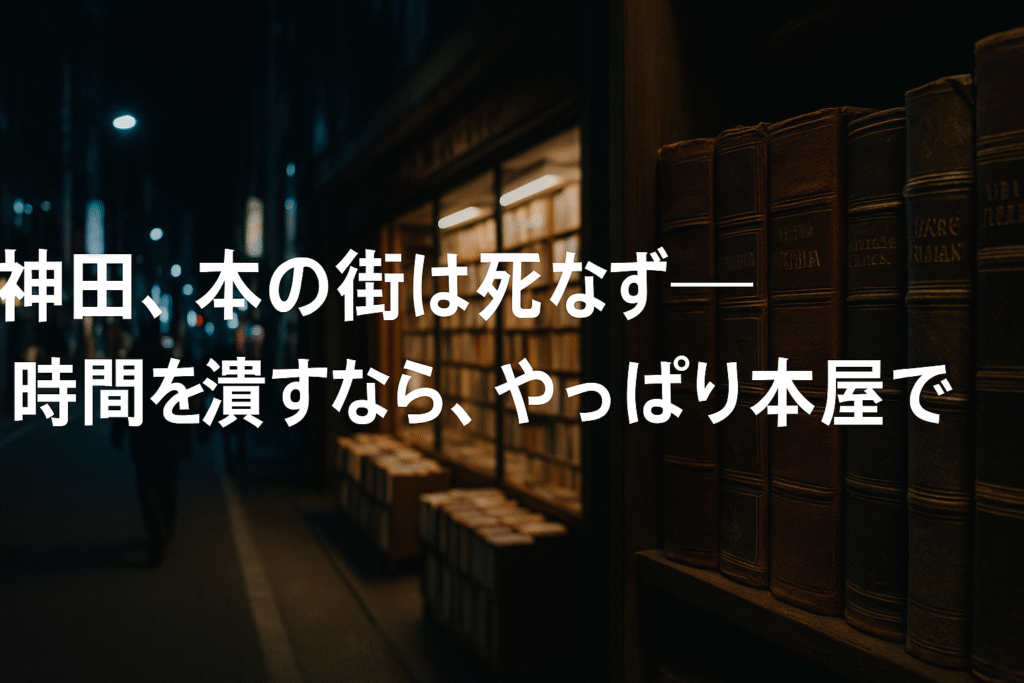
時間を潰すなら、本屋だった。
コヨーテが大阪に住んでいた頃、街を歩けばそこかしこに本屋があった。
阿倍野では旭屋書店、梅田なら紀伊國屋書店。
ガールフレンド(今の妻)との待ち合わせ、悪友と飲みに行く前のひととき。
家の近くの本屋で雑誌を一冊買って帰る──
そんなささやかな日常が、いまは遠い昔の風景のようだ。
あの頃、本屋は“街の温度計”だった。
平積みされた雑誌や新刊の並びで、時代の空気がわかった。
子ども向けコーナーから受験参考書、文庫棚へと興味が移るたび、
その変化を静かに見守ってくれていたのも本屋だった気がする。
けれど今、街から本屋が消えている。
小さな書店は壊滅的で、商店街の灯が一つずつ消えていくようだ。
それでも、東京にはまだ「本の街」が残っている。──神田・神保町だ。音楽を読む場所があった

それでも、神田は終わらない
しかし神保町は、静かに形を変えながら再生している。
古本の街が、いまは“知の実験都市”になりつつある。
その先頭を走るのが「PASSAGE by ALL REVIEWS」。
批評サイト「ALL REVIEWS」と連携し、
作家や編集者、批評家たちが交わるサロンのような空間。
本を「売る」よりも「語る」「考える」ための場所だ。
イベントでは、読者が議論に参加する。
もはや“書店”というより、“リアルな思想のSNS”だ。

そしてもう一軒、「本まる書店」。
出版社出身の店主が、出版者と読者を直接つなぐ試みを続けている。
ここでは作り手が直接棚に立ち、本の背景を語る。
まるで“出版社が街角に出てきた”ような感覚だ。
神保町の新しい風景の中心に、この店がある。
ほんがある日は一日がまる・本や棚主と出会い・ほんまる神保町ほんまる神保町のウェブサイト。「ほんがある日は一日がまる」という思いも込めて新しい本と出会って欲しいとの思いから、本を愛すwww.honmaru.me

本の街が教えてくれること
古賀書店が消え、PASSAGEや本まるが生まれた。
そこには“消費の終わり”ではなく、“再定義の始まり”がある。
AIがどれだけ賢くなっても、
誰かが「この一冊は読むべきだ」と手渡す瞬間は、
人にしかできない。
コヨーテが昔、時間を潰していたあの本屋の静けさ。
あれは単なる暇つぶしではなく、
「自分と向き合うための時間」だったのかもしれない。
神田の街角で本をめくっていると、
あの頃の自分が、少しだけ隣に戻ってくる。
だから今日も思う。
──時間を潰すなら、やっぱり本屋がいい。
そして、神田がその最後の砦であってほしい。