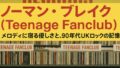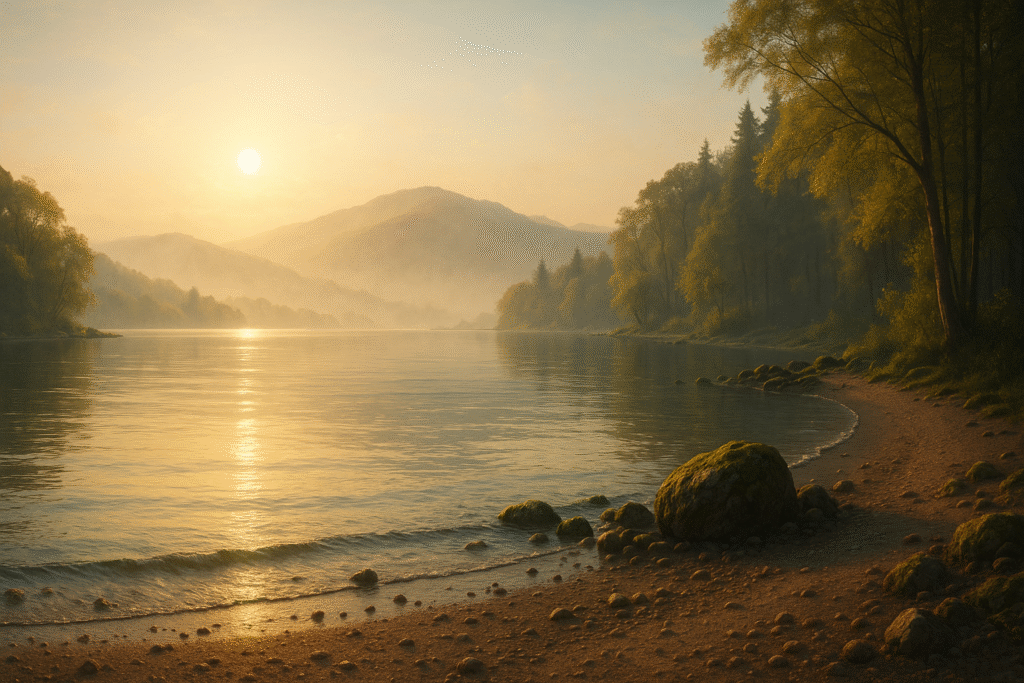
11月4日はフェリックス・メンデルスゾーンの命日。
ロマン派の旗手ということで、作風や曲調は確かにシューマンと似ている。
村上春樹の「色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年」にも
「メンデルスゾーンとシューマンの音楽を聴き分けられることができた」
という一文が出てくる。
確かにね、あの二人の音楽はどちらも情感豊かなんだけど、
聴いていると違う景色が見える気がする。
コヨーテはクラシックについてはそれほど聴き込んできたわけじゃないけれど、
メンデルスゾーンの「美しすぎる旋律」に比べると、
シューマンにはどこか「狂気」とか「衝動」みたいなものが潜んでいる気がする。
まあそういう人生だったからね。
メンデルスゾーンはその対極にある。整っていて、優雅で、でも冷たくはない。
天才少年のまま駆け抜けた人生
1809年、ドイツ・ハンブルクの銀行家の家に生まれた。
祖父は哲学者モーゼス・メンデルスゾーン。
つまり名門中の名門。幼いころから英才教育を受けて、9歳で公開演奏。
13歳で弦楽八重奏曲。もうこの時点で完成してる。
生活にはまったく困っていなかったから、
ベートーヴェンやシューベルトみたいな「貧苦からの創作」とは無縁。
彼の音楽に「苦悩の影」が薄いのは、たぶんそういう育ちもある。
でもその分、構築的で、端正で、澄んだ感情がある。
1830年代にはライプツィヒ音楽院を作って、
教育者としても活動していた。38歳で亡くなったのが信じられないくらいの仕事量だ。
美の構築者
メンデルスゾーンの曲を聴いていると、
「よくできた美しさ」という言葉がぴったりくる。
感情の爆発というより、形の中に感情を閉じ込めた感じ。
たとえば序曲「フィンガルの洞窟」。
海を描いているのに、荒れ狂う波じゃなくて、
光と霧と静かなうねり。
どの音も整っていて、乱れがない。
優等生すぎると言われることもあるけれど、
この均衡の取れたロマンティシズムが、むしろ今の時代には沁みる。
おすすめ曲
「ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 Op.64」
いわゆる「メンコン」。
有名すぎて逆にスルーしがちだけど、聴くとやっぱり圧倒的。
冒頭のヴァイオリンが流れ出す瞬間、世界がひとつ変わる。
おすすめはこの2つ。
• ヒラリー・ハーン(ヴァイオリン)/ネヴィル・マリナー指揮 アカデミー室内管弦楽団
→ 若いけれど音が透き通っていて、現代的。
• ヤッシャ・ハイフェッツ(ヴァイオリン)/トスカニーニ指揮 NBC交響楽団
→ 古い録音だけど、緊張感がすごい。まるで刃物のような音。
「交響曲第3番『スコットランド』 Op.56」
旅の記憶を音に変えた傑作。
メンデルスゾーンの内面が少しだけ顔を出している感じがして好きだ。
クラウディオ・アバド/ロンドン響盤がおすすめ。
「フィンガルの洞窟」序曲 Op.26
海の呼吸。
波の音を聴いているようで、心の中が静かになっていく。
ここはやっぱりクルト・マズアの盤を挙げたい。
ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団との録音(Philips)は、
透明感の中に深いスケール感があって、まさに“北の海”の空気そのもの。
音の奥に空間がある。これがメンデルスゾーンの真骨頂だと思う。
「無言歌集」より
これはピアノ曲集。派手さはないけど、どの曲も静かで美しい。
タイトルの通り「言葉のない歌」。
1曲ごとに短い物語がある。
夜に一人で聴くと、まるで日記を読んでいるような気分になる。
おすすめは「ヴェネツィアの舟歌」や「春の歌」。
田部京子の演奏は、まさに“優しさと内省の中間”にある音。
感情を押しつけないのに、心の奥にすっと届く。
この人のメンデルスゾーンを聴くと、「無言」という言葉の深さがわかる気がする。
おわりに
シューマンが“内面の嵐”を描いた人なら、
メンデルスゾーンは“理性と希望の人”だった。
村上春樹が書いたように、「聴き分けられること」は
単に耳の問題じゃなくて、心の質の違いを感じ取る力のことなんだろう。