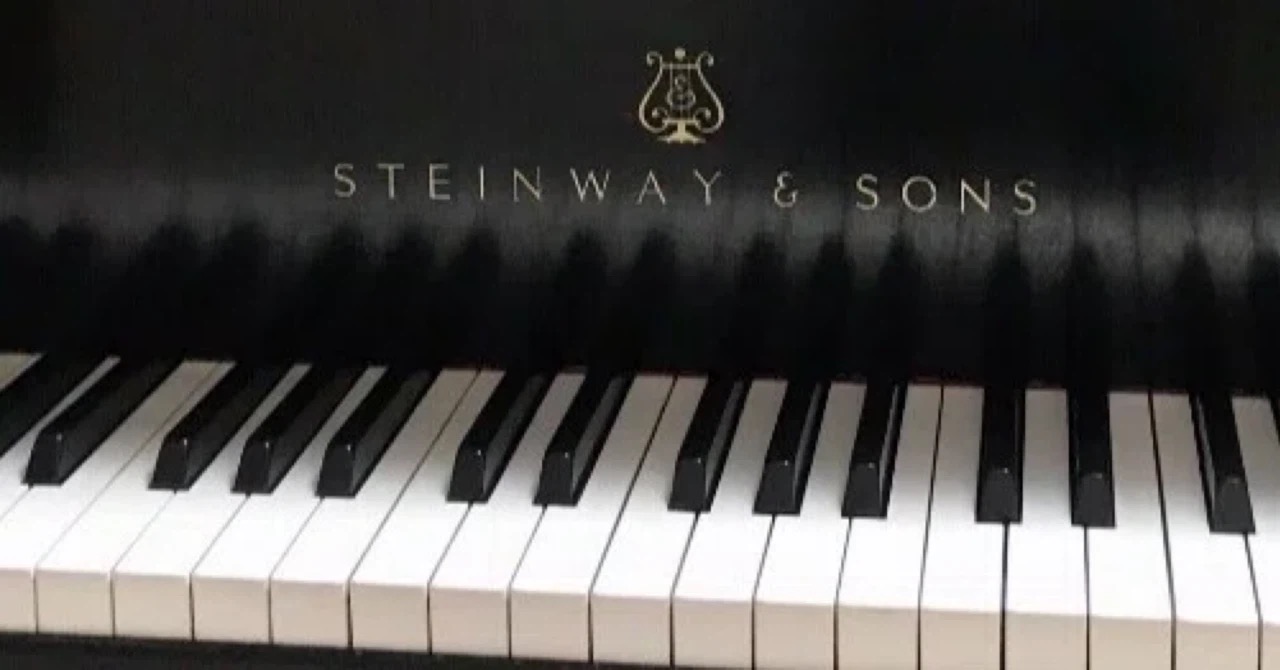シューマンの音楽ってどこがすごい?
ピアノの一音一音が、まるで心の声のように語りかけてくる。
ロベルト・シューマン(1810-1856)の音楽は、聴く人の感情を不思議なくらい揺さぶります。
今日は命日にあわせて、シューマンの人生とおすすめ音源を紹介します。
若き日の挫折と転機
シューマンは法学部に通いながらも、心は文学と音楽に夢中。
20歳の頃、指を鍛える器具で右手を痛め、ピアニストの夢は断たれました。(大リーグボール養成ギブスか?)
しかし、この挫折が作曲家としての道を切り開きます。
初期の代表作『パピヨン』作品2は、作家ジャン・パウルの小説に触発された作品。
文学と音楽が融合する、まさに「シューマンらしい」出発点です。
クララとの愛と闘い
師であるフリードリヒ・ヴィークの娘・クララとの恋は、父親の猛反対で法廷闘争にまで発展しましたが、1840年についに結婚。
この時期に生まれた『謝肉祭』作品9は、シューマン自身の分身「フロレスタン」と「オイゼビウス」、クララ、ショパンまでが登場する音の肖像画のような作品です。
特に内田光子の録音は必聴。全編、内面の静けさと情熱が交錯し、最後までドキドキさせてくれる演奏です。
家庭と創作の幸せな時間
8人の子どもと暮らす家庭生活は、創作の黄金期。
『子供の情景』作品15は、大人が子ども時代を懐かしく振り返るような13の小品。
アルゲリッチの1983年録音は、技巧よりも自然な語り口で、聴く人の心にすっと染み込む名演です。
また、ピアノ四重奏曲 変ホ長調 作品47も傑作。
グールドとジュリアード弦楽四重奏団の録音は、独特のアプローチでシューマン像を鮮やかに塗り替えています。第3楽章はため息が出るほどの美しさ。
精神の病と晩年の悲劇
40代に入ると、幻聴や躁鬱に苦しみながらも、深みのある作品を残しました。
交響曲第2番 ハ長調 作品61は、病との闘いの中で生まれ、苦悩と希望の両方が詰まった音楽です。
1854年にはライン川に投身する自殺未遂。
その後、精神病院で療養生活を送り、1856年7月29日、46歳でこの世を去りました。
狂気と芸術の境界線
シューマンの音楽は、彼の心の揺らぎや葛藤がそのまま芸術に昇華されているよう。
『クライスレリアーナ』や晩年のピアノ曲を聴くと、彼の内面の深い闇と光にそっと触れてしまうような感覚になります。
⸻
シューマンおすすめ音源3選
1. 『謝肉祭』作品9 – 内田光子(1994年録音)
内面の美と情熱を完璧に描き切った名演。
2. 『子供の情景』作品15 – マルタ・アルゲリッチ(1983年録音)
トロイメライの優しい響きが、心を温めます。
3. ピアノ四重奏曲 変ホ長調 作品47 – グレン・グールド&ジュリアード弦楽四重奏団(1968年録音)
個性がぶつかり合いながらも奇跡の調和を生む一枚。